
「理想の学校・教育とは?」子供達から1万件の声を集めた長崎県|教育振興基本計画×実践事例レポート⑩
教育振興基本計画に基づく各地域の実践事例をご紹介する本連載。第10弾は、長崎県です。
2023年6月に策定された国の第4期教育振興基本計画では、「各ステークホルダー(子供を含む)からの意見聴取・対話」を重視する方針が新たに記載されました。
長崎県では、県の計画策定の過程で児童生徒への大規模なアンケートを実施したそうです。どんな方法を取ったのか、どんな苦労があったのかなど、長崎県教育庁教育政策課のご担当の方に詳細を伺いました。
===
「ウェルビーイングの向上と共生社会の実現」を目指す長崎県
――長崎県の教育政策について概要を教えてください。
長崎県では、令和6年3月に、令和6年度から令和10年度までの5年間の計画として、「第四期長崎県教育振興基本計画」を策定しました。分量は30ページほどのとてもコンパクトな計画で、必要な内容や図などが見やすくレイアウトされています。

この計画のコンセプトは「つながりが創る豊かな教育」です。多くの人とのかかわりから生まれる学びの機会や地域コミュニティの活力などを大事にしています。社会の多様化が進む中で、一人一人が豊かで幸せな人生と社会の持続的な発展を実現できるように、「ウェルビーイングの向上と共生社会の実現」を目指すべき方向性として視野に入れています。
その一環として、この計画では「こども基本法」を踏まえた対応の必要性を盛り込み、実際に計画策定の段階から子供の意見を取り入れるようにしました。
「子供たちの言葉で回答をしてほしい」
――子供の意見聴取はどのような経緯で行われたのでしょうか。
長崎県では、令和5年4月にこども基本法が施行されて以降、国からの通知等の周知を受けて、法に基づいて子供の意見を聴く機会を設ける必要があることを認識していきました。しかし、どういう設問で、どういう方法で聴いたらいいかなど、具体的なことはなかなかイメージができず、他県の取組などを見ながら手探りで検討をしていきました。こども政策所管部署とも連携して設問の検討を進めました。
「子供から意見を聴くからには、子供たちの言葉で回答をしてほしい」と教育庁の中で意見が出て、自由記述を1問含む全16問でアンケートを作成しました。
――アンケートはどのような方法で実施しましたか。
調査は学校に実施を依頼する場合が多いですが、このアンケートでは学校になるべく負担をかけずに行う方法を考え、Webのアンケート作成ツールを使用しました。児童生徒の回答を学校に集約してもらわずに、直接、県教育委員会の担当に届くようにしたのです。そうすることで子供たちも意見を言いやすくなるのではないかとも考えました。
教育振興基本計画は公立・私立両方の学校が対象であるため、私立学校の所管部署とも連携して周知を行いました。
アンケートは一人一台端末を使って回答してもらう想定でしたが、市町のセキュリティによって児童生徒がアンケートフォームにアクセスできない場合もあります。そういった場合は、児童生徒が自宅からでも回答できるようにQRコードを付けたチラシを用意するなどの工夫もしました。
結果として10,026名から回答をいただきました。特に、学校や教育についての自由記述では5,560名から6,077件ものご意見をいただくことができました。
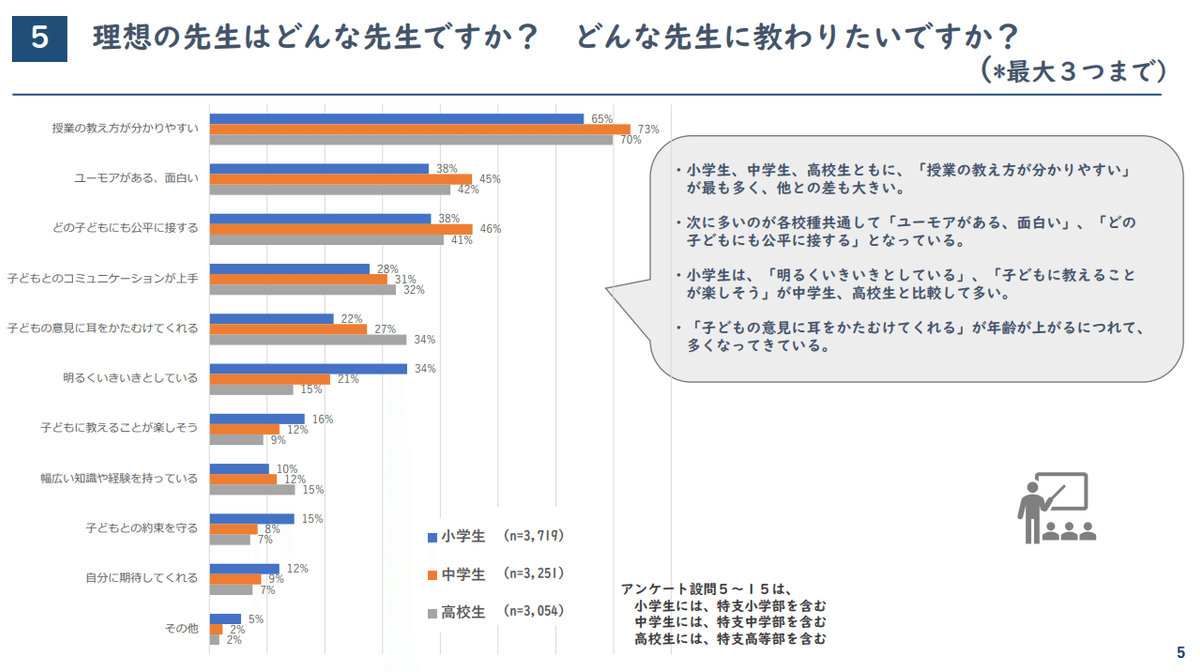
――1万を超える子供の声が集まったのですね。集計や分析は大変ではなかったですか。
アンケート作成ツールを使用したことで、アンケート結果は基本的に自動集計ができました。一方で、子供たちが自身の言葉で意見を言えるようにするために自由記述を盛り込んだため、その集約は手作業が必要でした。
集約を外部委託する予算も確保していなかったため、班員で手分けをして、各意見の趣旨に合わせた分類を行う作業を行いました。「授業や宿題など勉強に関すること」「学校の施設や設備、教室利用に関すること」など10項目ほど想定される項目を用意したうえで、1点1点回答を読み、項目に割り振る形で作業をしていきました。しかし、どうしても想定外の分類が必要になることや、趣旨が少しあいまいな意見などもあるので、その際は主担当が全体調整を行いました。

――振り返ってみて、改善できると思われるところもありますか。
改善可能な点としては、児童生徒から自由記述を回答してもらう段階で意見の分類項目を選択できるようにしていたら、もう少し作業が円滑だったかもしれません。
しかし、実際に1点1点読むことで子供たちの声が直接わかり、負担は大きくとも得るものは大きかったです。
アンケートの集計後は、子供たちの声が計画に反映されている状況がわかるように資料としてまとめ、ホームページで公表をしました。一方で、子供たちに意見を出した意義を感じてもらえるように、結果を直接伝える方法も考えていきたいです。そのことが子供たちの学校・教育に関しての継続的な参画につながると考えます。

子供の意見を聴く取組の浸透
――取組は今後広がっていくでしょうか。
今年度は、国のこども大綱を勘案して策定することとなっている、県こども計画の策定にあたって、こども政策所管部署を中心に子供アンケートが進められています。連携する部署もこれまでよりも増える見込みで、県庁内で少しずつ子供の意見を聴く取組が広がってきていると感じています。
また、希望する市町教育委員会に対しては、県が行ったアンケートのうちその市町に住む児童生徒の回答状況を共有する旨を周知しており、市町教育委員会でもアンケート結果を政策に活用することが可能となっています。こうして、市町と県とで重複したアンケートを行うことがないよう連携しつつ、市町教育委員会における子供の意見を聴く取組の後押しにもつながっていくことを期待しています。
子供が参画する学校教育
――他に進められている取組はありますか。
このアンケートで得た意見や子供たちの主体性を大切にしていきたい思いから、今回策定した教育振興基本計画の主要施策に「児童生徒が主体的に参画する学校づくりの推進」を新たに盛り込み、始まった取組が「モデル校による新たな学校運営の実践事業(イノベーションハイスクール)」です。
この事業は、「生徒主体の学校づくり」と「教職員の働き方(がい)改革 」をかけ合わせ、生徒の柔軟で発想力豊かな意見をくみ取り、主体的に学びや学校行事をイノベートし続けることを目指すもので、生徒も教職員も固定観念にとらわれない新しい学校づくりにチャレンジし始めています。
例えば、長崎県立長崎東中学校・高等学校では中学では年に6回、高校では年に9回の「ひがしチャレンジデー」という日を設け、授業や部活動を行わず、生徒や教員がそれぞれ自ら立てた計画に従って1日を過ごす取組を行っています。生徒たちは、自分の関心に従って普段の授業とは異なる学習を行ったり、校外の様々な活動に参加したりするなど、自主的に取組を決めています。この日は多くの教員が年休を取得して、心身のリフレッシュや自己研鑽に充てたり、地域の活動に参加したりしています。
現在は検証をしながら進めている取組ですが、このように、生徒の主体性に任せる取組も進められています。
===
子供を主体とした長崎県の取組をご紹介しました。
多くの自治体で、子供の意見の集め方や取り入れ方を検討されているところだと思います。今後も関連情報を発信していきます。
……………………………………………
読者アンケート: 「ミラメク」で取り上げてほしいテーマ(施策解説、話を聞きたい人物、魅力的な地域のプロジェクト)等、御意見・御要望をお寄せください。

